不用品回収と一般廃棄物の違いを環境省基準で徹底解説|違法業者の見分け方と正しい処分
「不用品回収 一般廃棄物」でお悩みの方へ。本記事は、環境省の基準と廃棄物処理法を軸に、一般廃棄物と産業廃棄物の違い、自治体の役割、収集運搬業許可・許可番号の確認、粗大ごみ・資源ごみ・有害ごみの区分までを一望できる決定版です。家庭ごみで自治体委託業者しか収集できないもの、家電リサイクル法・小型家電リサイクル法・パソコンリサイクルの正しい出し方、事業系一般廃棄物の委託契約の要点と料金の目安、オフィス移転や店舗閉鎖・建設系残材で産廃に当たるケース、マニフェストや中間処理・最終処分の確認、無許可の無料回収や軽トラック巡回の見分け方、見積書・契約書で見るべき項目、不法投棄や高額請求時の相談先(消費者ホットライン188・各自治体窓口)まで具体的に解説。結論は、家庭由来の一般廃棄物は自治体ルート、事業系一般廃棄物は自治体許可業者と契約、産業廃棄物は許可業者とマニフェストで処理するのが最短・最安全です。
不用品回収と一般廃棄物の違いの全体像

まず押さえておきたいのは、「不用品回収」は法律上の区分名ではなく民間サービスの総称であるのに対し、「一般廃棄物」は環境省所管の廃棄物処理法に基づく法的な分類であるという点です。同じ「要らない物」でも、法区分(一般廃棄物か産業廃棄物か)、自治体ルール(分別・収集方法・手数料)、個別リサイクル法の適用有無によって、正しい処分ルートと委託できる業者が変わります。
本章では、環境省の基準を軸に、一般廃棄物と産業廃棄物の定義、自治体の役割と許可制度、さらに「粗大ごみ・資源ごみ・有害ごみ」の区分を整理し、「不用品回収」というサービスとの関係を誤解なく理解できる全体像を示します。
環境省の基準と廃棄物処理法の位置づけ
廃棄物処理法は、廃棄物の適正な処理・再資源化を目的に、廃棄物の区分、排出者の責務、自治体と許可業者の役割を定めています。環境省は同法に基づき通知やガイドラインを示し、全国の市区町村・都道府県がそれを踏まえて、一般廃棄物処理計画、分別区分、収集頻度、手数料(指定袋・粗大ごみ券など)を定めます。
不用品回収業者が取り扱えるかどうかは、法区分と許可の有無で決まります。家庭や事業所から出る「一般廃棄物」は、市町村の責任で処理されるのが原則で、収集運搬・処分は市町村の直営か委託、または市町村長の許可を受けた一般廃棄物処理業者のみが取り扱えます。一方、事業活動に伴う「産業廃棄物」は、排出事業者に処理責任があり、都道府県知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)で流れを管理します。
一般廃棄物と産業廃棄物の定義
廃棄物は、発生源と性状で大別されます。家庭から出る生活ごみの多くは「家庭系一般廃棄物」、事業所から出るごみのうち法定20種類の産業廃棄物に該当しないものは「事業系一般廃棄物」、そして事業活動に伴い生じ、法で定める20種類に該当するものが「産業廃棄物」です。また、爆発性・毒性・感染性など特に危険性の高いものは「特別管理(一般/産業)廃棄物」として厳格に扱われます。
| 区分 | 主な発生源 | 処理責任 | 許可・管理 | 典型例 |
|---|---|---|---|---|
| 家庭系一般廃棄物 | 家庭(生活由来) | 市区町村 | 市区町村の直営・委託、または市町村長許可の一般廃棄物処理業 | 可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみなど |
| 事業系一般廃棄物 | オフィス・店舗などの事業活動(ただし産業廃棄物に該当しないもの) | 市区町村(収集体系)と排出事業者(分別・委託) | 市町村長許可の一般廃棄物収集運搬業者との契約等 | 紙ごみ、飲食店の生ごみ等(産業廃棄物に該当しないもの) |
| 産業廃棄物 | 工場・建設現場・オフィスなどの事業活動 | 排出事業者 | 都道府県知事等の許可(収集運搬・処分)、マニフェストで管理 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、がれき類、汚泥、廃油 等 |
| 特別管理(一般/産業)廃棄物 | 一般・産業いずれも対象(有害・感染性・爆発性など) | 区分に応じて市区町村または排出事業者 | 特別管理の基準に適合した収集運搬・処分 | 一定の有害物質を含むもの等(所定の基準・手続に従う) |
事業活動で出たごみでも、法定20種類に該当しない限りは「事業系一般廃棄物」となり、市区町村の分別・収集ルールに従う必要があります。逆に家庭の片付けでも、リフォームで生じた建設系残材などは産業廃棄物に当たる場合があるため、発生状況と品目の見極めが重要です。
自治体の役割と収集運搬業許可の種類
一般廃棄物の処理責任は市区町村にあります。各自治体は「一般廃棄物処理計画」に基づき、分別区分、ステーション収集や戸別収集の実施、粗大ごみの予約制、クリーンセンター等への自己搬入の受入条件、手数料(有料指定袋・処理券)を定め、指導監督を行います。
収集や処理を担う事業者には許可制度があり、対象や管轄が異なります。以下は主要な許可の整理です。
| 許可区分 | 対象廃棄物 | 管轄 | 主な業務 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業 | 一般廃棄物(家庭系・事業系) | 市町村長 | 市区町村の収集体系に基づく収集運搬 | 市区町村ごとに許可が必要(エリア限定) |
| 一般廃棄物処分業 | 一般廃棄物 | 市町村長 | 焼却・破砕・選別・埋立等 | 公設処理施設の運営委託など |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 産業廃棄物 | 都道府県知事・政令市長 | 産業廃棄物の収集運搬 | マニフェストによる管理が必要 |
| 産業廃棄物処分業 | 産業廃棄物 | 都道府県知事・政令市長 | 中間処理・最終処分 | 施設ごとに許可が必要 |
| 特別管理産業廃棄物(収集運搬・処分) | 特管産業廃棄物 | 都道府県知事・政令市長 | 厳格な基準での運搬・処理 | 専用の許可・基準に適合 |
一般廃棄物の収集運搬を民間に委ねる場合、その事業者は市町村長の許可(または委託)を受けている必要があります。産業廃棄物の許可だけでは、一般廃棄物を収集することはできません。また、買取(リユース)を行う場合は、別途「古物商許可」が必要になることがありますが、これは廃棄物の収集運搬許可とは目的が異なる点にも留意してください。
粗大ごみと資源ごみと有害ごみの区分
家庭から出る一般廃棄物は、自治体の分別ルールにより「可燃・不燃」だけでなく「粗大ごみ」「資源ごみ」「有害ごみ」などに細分化されます。名称や対象品目、サイズ・重量基準、出し方(予約制・ステッカー貼付など)は自治体ごとに異なるため、必ずお住まいの市区町村のルールを確認してください。
| 区分 | 典型的な品目例 | 出し方の基本 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 粗大ごみ | 家具(タンス・ベッド・ソファ)、大型家電(掃除機・電子レンジ等)、自転車 | 事前申込み制や有料処理券の貼付、戸別収集または自己搬入 | サイズ・重量の基準は自治体で異なる。解体の可否も要確認 |
| 資源ごみ | 古紙(新聞・雑誌・段ボール)、びん・缶、ペットボトル、衣類、小型金属 | 分別・洗浄・束ねる・透明袋など自治体指定の方法で排出 | 異物混入は資源化を妨げるため厳禁。曜日・集積所の指定あり |
| 有害ごみ | 乾電池、蛍光灯・LED管、水銀式体温計、スプレー缶・カセットボンベ | 専用ボックスや指定日に分けて排出、穴あけ不要の運用が増加 | 破損・漏洩防止の梱包が必要。事業所排出は扱いが異なる場合あり |
なお、冷蔵庫・洗濯機・エアコン・テレビのいわゆる家電4品目は「家電リサイクル法」の対象であり、自治体の粗大ごみでは原則収集されません。パソコンはメーカー等による回収ルート(資源有効利用促進法等)、携帯電話や小型電気製品の一部は「小型家電リサイクル法」の対象など、個別リサイクル法が優先する品目もあります。分別区分は自治体、適用法は国の制度と複層的に関わるため、「品目」と「発生状況」を起点に、最適な処分ルートを選ぶことが重要です。
以上を踏まえると、民間の不用品回収サービスを利用する際も、依頼品が「一般廃棄物」か「産業廃棄物」か、個別リサイクル法の対象か、自治体ルールでどう扱われるかを確認することが、適法・適正でコスト効率の良い処分につながります。
不用品回収で扱えるものと扱えないもの

「不用品回収」で合法的に扱える範囲は、自治体の一般廃棄物収集運搬業許可や各種リサイクル法のルートに適合しているかで決まります。 同じ「不要品」でも、廃棄物処理法上の一般廃棄物・産業廃棄物・有価物(再利用目的の中古品)で扱いが分かれ、家電リサイクル法・小型家電リサイクル法・パソコンリサイクル(資源有効利用促進法)など個別法の対象品は専用の回収ルートのみが正規の処分方法となります。
無許可での戸別回収や「無料回収」をうたう巡回回収は、一般廃棄物の収集運搬では違法となる典型例です。 まずは下の一覧で「誰が・何を・どの条件で」扱えるかを確認してください。
| 区分 | 主な例 | 不用品回収業者が扱える条件 | 扱えない・要注意 | 根拠・所管 |
|---|---|---|---|---|
| 家庭系一般廃棄物(可燃・不燃) | 生活ごみ、衣類、割れた食器、プラスチック小物など | 排出地の市区町村が許可した一般廃棄物収集運搬業者であること。自治体と委託契約に基づく収集。 | 無許可業者の戸別回収・無料回収・軽トラ巡回は不可。 | 廃棄物処理法、自治体条例 |
| 家庭系粗大ごみ | 家具・寝具・自転車・カーペットなど | 自治体の粗大ごみ受付(手数料券)または自治体許可業者の収集。 | 無許可の引き取りやその場での高額請求に注意。 | 廃棄物処理法、自治体条例 |
| 資源ごみ | 新聞・雑誌・段ボール、びん・缶、ペットボトル、古着 | 自治体回収・地域集団回収・登録古紙回収業者など正規のルート。中古品としての買取は古物商許可が必要。 | 廃棄物と混載しての回収は一般廃棄物扱いとなり、無許可では不可。 | 廃棄物処理法、資源物回収指針、古物営業法 |
| 有害ごみ | 乾電池、小型充電式電池、蛍光管、水銀体温計、スプレー缶 | 自治体の有害ごみ回収・店頭回収(電池など)・指定拠点への持込み。 | 一般の不用品回収業者が無許可で回収することは不可。 | 自治体条例、関係指針 |
| 家電リサイクル法対象4品目 | エアコン、テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機 | 小売店ルート(買替え・販売店引取)または指定引取場所への搬入。回収を委託する場合は、法に基づくルート・家電リサイクル券の手続きが必要。 | 自治体の通常収集や無許可業者への引渡しは不可。 | 特定家庭用機器再商品化法 |
| 小型家電リサイクル法対象品 | 携帯電話・スマートフォン、デジカメ、ゲーム機、ドライヤー、電子辞書など | 自治体の回収ボックス・拠点回収、または認定事業者の回収。 | 無許可の出張回収や路上回収は不可。データ媒体は要消去。 | 小型家電リサイクル法 |
| パソコン(家庭) | デスクトップ、ノートPC、ディスプレイ(CRT・液晶) | メーカー回収(PCリサイクルマーク有は無料、無は料金要)等の正規ルート。ゆうパック集荷等の手順に従う。 | 自治体の粗大ごみ対象外。無許可業者の回収は不可。 | 資源有効利用促進法(PCリサイクル) |
| 事業系一般廃棄物 | オフィスごみ、飲食店の生ごみ、事業活動に伴う紙くず等 | 排出事業者が、許可を持つ一般廃棄物収集運搬業者と契約し、定期収集または持込み。 | 家庭ごみ回収への混入は不可。産業廃棄物との混合も不可。 | 廃棄物処理法、自治体条例 |
| 産業廃棄物に該当するもの | 建設工事の廃材、オフィス改装の残材、事業活動に伴う特定品目 | 本章の対象外(産業廃棄物許可業者・マニフェストが必要)。 | 一般の不用品回収業者(一般廃許可のみ)では不可。 | 廃棄物処理法(産業廃棄物) |
家庭由来の一般廃棄物の取り扱い
家庭から出る一般廃棄物は、市区町村が処理責任を負い、自治体自らの収集または自治体が許可・委託した一般廃棄物収集運搬業者のみが収集できます。引越しや家財整理で大量に出る場合でも、「家庭系一般廃棄物」を有料で戸別回収できるのは、当該自治体の許可を持つ業者だけです。中古として再利用が明らかな「有価物」は買取が可能ですが、廃棄物と混載すると一般廃棄物扱いとなり許可が必要になります。
自治体委託業者のみが収集できるもの
一般的な家庭ごみの多くは、自治体の分別ルールに従って定期収集または粗大ごみ受付で処理します。以下は典型例と注意点です(具体の分別名称・持ち出し日・手数料は自治体により異なります)。
| 分別区分 | 主な品目例 | 収集主体 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 可燃ごみ | 生ごみ、汚れた紙、少量の木片・革・ゴムなど | 自治体または自治体許可の収集運搬業者 | 事業系と混ぜない。台所ごみ等の戸別回収を無許可業者に依頼することは不可。 |
| 不燃ごみ | 陶器・ガラス、金属小物、刃物など | 自治体または自治体許可の収集運搬業者 | 割れ物は安全に配慮して袋や新聞紙で包む等、自治体の出し方に従う。 |
| 資源ごみ | 新聞・雑誌・段ボール、びん・缶、ペットボトル、古布 | 自治体回収、地域集団回収、登録古紙回収業者 | 汚れた資源物は可燃ごみへ。廃棄物と混載しての回収は一般廃棄物扱い。 |
| 有害ごみ | 乾電池、小型充電式電池、蛍光管、水銀体温計、スプレー缶 | 自治体の専用回収日・拠点回収・店頭回収 | 穴あけ禁止の自治体あり。一般の不用品回収業者に出さない。 |
| 粗大ごみ | 家具、寝具、自転車、じゅうたん等(自治体規定の寸法・重量超) | 自治体の予約制収集または持込み | 手数料券の掲示が必要。戸別回収代行は当該自治体許可業者のみ可。 |
家電リサイクル法対象品目
エアコン、テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、一般の粗大ごみや通常収集では出せません。正規の処分は「小売店ルート」または「指定引取場所」への搬入で、リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。依頼先が不用品回収業者であっても、家電リサイクル券の発行・貼付など法定手続に沿っているかを必ず確認します。
| 品目 | 代表的な製品 | 正しい回収ルート | 費用の考え方 | 関与事業者 |
|---|---|---|---|---|
| エアコン | 壁掛け・窓用・床置き型 | 買替え時の販売店引取、または指定引取場所へ搬入 | リサイクル料金+収集運搬料金 | 小売店、指定引取場所、運搬委託事業者 |
| テレビ | ブラウン管、液晶、プラズマ | 買替え時の販売店引取、または指定引取場所へ搬入 | リサイクル料金+収集運搬料金 | 小売店、指定引取場所、運搬委託事業者 |
| 冷蔵庫・冷凍庫 | 1ドア~大型、冷凍庫 | 買替え時の販売店引取、または指定引取場所へ搬入 | リサイクル料金+収集運搬料金 | 小売店、指定引取場所、運搬委託事業者 |
| 洗濯機・衣類乾燥機 | 縦型・ドラム式、乾燥機 | 買替え時の販売店引取、または指定引取場所へ搬入 | リサイクル料金+収集運搬料金 | 小売店、指定引取場所、運搬委託事業者 |
チェックポイント(依頼前に確認)
- 家電リサイクル券の手配(販売店手続または所定の方法による発行)が行われるか。
- 引取り業者が自治体の一般廃棄物収集運搬許可を持つか、または小売店等の法定ルートでの運搬か。
- 「無料回収」をうたう無許可の引取りに渡さない(不法投棄・高額請求のリスク)。
小型家電リサイクル法対象品目
小型家電リサイクル法は、使用済み小型電気電子機器に含まれる貴金属・レアメタルを回収するための制度です。自治体の回収ボックスや拠点回収、認定事業者による回収が正規ルートです。不用品回収業者に依頼する場合は、自治体の許可・委託や認定事業者としての位置づけがあるかを必ず確認してください。
| 区分 | 主な品目例 | 回収方法 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 情報機器 | 携帯電話・スマートフォン、タブレット、外付けHDD、デジタルオーディオ | 自治体回収ボックス、認定事業者の回収 | 個人情報のデータ消去(初期化・記憶媒体の取り外し)を徹底 |
| 小型家電 | デジカメ、ゲーム機、電動シェーバー、ドライヤー、炊飯器(小型)など | 自治体拠点回収、販売店の店頭回収(実施店舗のみ) | 混合廃棄は不可。電池は外して有害ごみ・店頭回収へ |
| 周辺機器 | キーボード、マウス、ACアダプタ、ケーブル | 自治体拠点回収、認定事業者回収 | 袋詰め・まとめ方は自治体の指定に従う |
「無料でその場で回収します」等の路上回収は制度外です。必ず自治体・認定事業者のルートを利用してください。
パソコンリサイクルと回収方法
家庭用パソコンは資源有効利用促進法の対象で、自治体の粗大ごみでは原則収集できません。PCリサイクルマークの有無に応じ、各メーカーの窓口で回収手続きを行い、指定の方法(例:ゆうパック集荷)で返送します。ディスプレイ(CRT・液晶)も対象です。自作PCや販売終了メーカー品は、指定団体の受付手順に従います。
- 手順の要点:メーカー申込 → ラベル受領 → 梱包 → 集荷依頼 → 引き渡し。
- 費用:PCリサイクルマーク有は回収・再資源化料金が不要、無は所定の料金が必要。
- データ対策:記憶媒体の初期化・物理破壊など、個人情報保護を徹底。
事業系一般廃棄物と排出事業者の責任
店舗・オフィス・施設等から出る事業系一般廃棄物は、排出事業者責任に基づき、許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者へ適正に委託する義務があります。家庭ごみの回収に混入することや、産業廃棄物と混合して排出することは禁じられています。自治体の処理施設へ自己搬入できる場合もありますが、搬入手続・分別基準・搬入可能品目は自治体の定めに従います。
委託契約書と処理委託の注意点
事業系一般廃棄物の委託では、契約前に次の点を確認します。
- 許可の適合性:収集運搬業者の「一般廃棄物収集運搬業許可」の有無、許可自治体、許可の有効期限、車両表示。
- 対象物の明確化:可燃・不燃・資源の区分、排出量の見込み、保管方法、回収容器の種類。
- 収集条件:収集曜日・時間帯、回数、臨時回収(スポット)の扱い、搬入先施設。
- 料金と計量:料金体系(袋・容器・重量・回数)、最小回収単位、追加費用の発生要件。
- 帳票と証憑:引取伝票・計量票・領収書の発行、苦情・事故時の連絡体制。
- 混合禁止:産業廃棄物に該当するものを混ぜない(マニフェストは産業廃棄物のみ)。
- 契約条項:契約期間、更新・解約条件、分別不適合時の対応、再資源化の方針。
「一般廃棄物」と明記のない見積書・契約書や、許可の提示を渋る業者は避けるのが安全です。
料金の目安と収集頻度
料金や頻度は自治体や事業形態・排出量で大きく変わります。多くの地域で採用される代表的な料金・契約方式は次のとおりです。
| 契約方式 | 料金の考え方 | 特徴・向いている事業 |
|---|---|---|
| 指定袋制 | 自治体または委託先指定の袋(容量別)単価で精算 | 小規模オフィス・小売。分かりやすいが、排出量が多いと割高になりやすい。 |
| 容器(コンテナ・バッカン)制 | 容器サイズごとの回収単価(1回あたり) | 飲食・小売・施設など中量以上。回収効率が高く、人件費を抑えやすい。 |
| 計量(重量)制 | 持込み・回収ごとに重量計量し単価を乗算 | 排出量の変動が大きい事業に適合。実量課金で公平性が高い。 |
| スポット回収 | 臨時の大量排出を個別見積り | 棚卸・レイアウト変更時など。通常契約と併用が一般的。 |
収集頻度は「週1回・週数回・毎日」など、営業時間・保管スペース・臭気対策(生ごみ)に応じて設定します。資源物(段ボール・古紙・びん缶ペット)は可燃ごみと分けて別契約・別日程にすることで、総コストの低減と再資源化率の向上が見込めます。
料金・頻度・分別ルールは自治体の基準と委託先の許可範囲に左右されるため、見積段階で許可証・収集ルート・処理先の確認を必ず行いましょう。
産業廃棄物に該当するケースの見極め

不用品回収の現場では、同じ「片付け」でも、排出形態や発生要因によって一般廃棄物と産業廃棄物の区分が変わります。区分を誤ると、無許可収集・不法投棄・マニフェスト未交付といった法令違反に直結します。
最初に確認すべきは「誰の活動で生じたか(家庭か事業か)」「工事等に伴うか」「政令で定める20品目に該当するか」の3点で、これが産業廃棄物該当性の入口になります。
- 発生主体を確認する(家庭由来か、事業活動に伴うものか)。事業活動で生じた廃棄物は、産業廃棄物または事業系一般廃棄物のいずれかになります。
- 廃棄物の種類を特定する(政令で定める産業廃棄物の品目・性状に該当するか、特別管理産業廃棄物に該当しないか)。
- 工事(新築・改修・解体・内装撤去)に伴って発生していないかを確認する。工事に伴う発生物は原則として産業廃棄物です。
- 特定リサイクル法の専用ルート(家電リサイクル、パソコン、フロン類、容器包装等)が優先される対象が混在していないかを仕分けする。
- 混合廃棄物であれば可燃・不燃、金属・木材・プラスチック等へ分別し、品目ごとに適正な許可と処理ルートを選定する。
- 産業廃棄物に該当する場合は、委託契約の締結とマニフェスト(紙または電子)の交付・最終処分確認を実施する。
- 契約書・マニフェスト・許可証写し等は原則5年間保存する(排出事業者の保存義務)。
「産業廃棄物なのに一般廃棄物として出してしまう」「混合のまま一括で回収させる」は、最も重大な不適正処理のパターンです。
オフィス移転や店舗閉鎖の混合廃棄物
オフィス移転や店舗閉鎖では、机・椅子・ロッカーなどの什器類、紙資料、販促物、パーテーション、照明器具、内装材など多様な廃棄物が同時に発生します。これらは「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」が混在しやすく、分別の判断を誤ると違法委託になりがちです。
| 発生品目の例 | 区分の目安 | 必要な許可・書類 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 机・椅子・ロッカー・棚などのオフィス家具 | 事業系一般廃棄物 | 自治体の「事業系一般廃棄物収集運搬」許可業者との委託契約 | 産業廃棄物許可のみの業者には委託不可(許可の種類が異なる)。 |
| パーテーション・什器の解体で出た部材(内装撤去を伴う) | 産業廃棄物(建設系:木くず、金属くず、廃プラスチック類等) | 産業廃棄物収集運搬・処分業の許可+マニフェスト | 内装解体や原状回復工事に伴う発生物は原則産業廃棄物。 |
| 紙資料・書類・段ボール(オフィスから) | 事業系一般廃棄物 | 事業系一般の許可業者へ委託 | 紙くずは特定業種由来のみ産業廃棄物。オフィス一般は「事業系一般」。 |
| 照明器具・蛍光管・水銀体温計など | 特別管理産業廃棄物(水銀使用製品産業廃棄物等) | 特別管理産業廃棄物の収集運搬・処分許可+マニフェスト(特管) | 破損防止の梱包・専用容器・保管表示が必要。混載禁止に注意。 |
| 業務用エアコン(撤去品) | 産業廃棄物に該当する部材+フロン類の適正回収が必要 | フロン類回収は有資格者による回収証明+産業廃棄物の許可・マニフェスト | フロン類回収・破壊の証明書類を保管。機器丸ごとの無許可回収は厳禁。 |
| パソコン・サーバー・周辺機器 | 専用リサイクルスキームの対象(メーカー回収等) | メーカー等の回収ルートの申込控え+データ消去証明 | 機密データの消去・証跡管理を徹底。一般・産業の混載排出は避ける。 |
現場で一括排出する場合は、回収前に什器類(事業系一般)と内装解体材(産業)を明確に分け、各々に適した許可業者と契約・手配をわけて進めます。
「軽トラックで無料回収・一括処分」をうたう無許可業者に混合のまま渡すと、排出事業者側も法令違反の当事者となります。
建設系残材とリフォーム廃材
建設工事(新築・増改築・原状回復・解体・設備更新)に伴って発生する残材や撤去材は、廃棄物処理法上の産業廃棄物に該当します。原則として、工事を請け負う事業者が排出事業者となり、分別・保管・委託・マニフェストまでの管理責任を負います。
| 代表的な発生物 | 産業廃棄物の品目例 | 実務上のポイント |
|---|---|---|
| コンクリートがら・アスファルトがら・レンガ | がれき類 | 土砂との混合防止。再生路盤材等への再資源化ルートを選択。 |
| 軽量鉄骨・配管・ダクト・ケーブル | 金属くず | 金属は単独分別で価値向上。被覆線は中間処理の可否を事前確認。 |
| 内装材・床材・塩ビクロス・断熱材・発泡スチロール | 廃プラスチック類 | 可燃・不燃の混合排出を避ける。塩ビ系は焼却不可先の有無に注意。 |
| 下地材・造作材・型枠材・廃パレット | 木くず | 含釘は可だが、石膏ボード混入は不可。含水率・塗装有無に留意。 |
| ガラス・陶磁器・タイル | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 破損飛散対策と保護梱包。土砂と混ぜない。 |
| 養生紙・段ボール・型紙(工事現場発生) | 紙くず | 工事由来の紙くずは産業廃棄物。オフィス由来の紙くずとは区別。 |
| 石膏ボード | (専用分別が必要) | 一般廃棄物と混合不可。専用回収・再生ルート・保管区画を確保。 |
| 塗料・溶剤・接着剤の残り、汚染ウエス | 廃油・廃酸・廃アルカリ等(特別管理に該当する場合あり) | 性状の把握とラベル表示。密閉容器での保管・専用許可とマニフェスト。 |
| 石綿含有建材の撤去材 | 石綿含有廃棄物(区分に応じて特別管理) | 事前調査・飛散防止措置・区分梱包・表示・適格許可の手配が必須。 |
小規模リフォームでも、壁・床・天井を剥がす内装撤去があれば建設系の産業廃棄物が発生します。発生品目の分別・仮置きの保管基準(飛散・流出・悪臭防止、表示、囲い等)を守り、積替え保管を行う場合は「積替え保管」の許可がある事業者に限定します。
建設混合廃棄物は、分別せずに一括処理を委託するのではなく、現場での一次分別を徹底することがコスト低減と法令適合の両立につながります。
マニフェストと収集運搬業許可の確認ポイント
産業廃棄物を委託する際は、「許可の適合」「委託契約」「マニフェスト」の三点を同時に満たす必要があります。特に許可は「品目」「区域(都道府県・政令市)」「積替え保管の有無」まで一致していることが必須です。
| チェック項目 | 確認書類 | 見るべき具体箇所 | 不適合時のリスク |
|---|---|---|---|
| 収集運搬業許可(産業廃棄物) | 許可証の写し | 許可品目(例:廃プラスチック類、木くず、金属くず等)/許可の有効期限/許可区域 | 無許可運搬は違法。排出事業者も処理義務違反の対象。 |
| 処分業許可(中間・最終) | 処分業許可証、処理フロー図 | 受入可能品目・処理方法(破砕・圧縮・溶融・焼却・再生)/施設所在地 | 受入不可品目の混入で受入拒否・不法投棄リスク。 |
| 特別管理産業廃棄物の許可 | 特別管理収集運搬業・処分業許可証 | 対象品目(水銀使用製品、廃酸・廃アルカリ等)/特管の表示 | 特管を一般産廃許可で扱うのは重大違反。 |
| 積替え保管の可否 | 許可証の「積替え保管」欄 | 積替え保管の有無/保管上限量/保管施設の所在地 | 無許可の積替え保管は違法。保管事故の責任拡大。 |
| 車両表示・処理施設の確認 | 車両写真、処理委託先一覧 | 事業者名・許可番号の表示/最終処分先の名称・所在地 | トレーサビリティ喪失。最終処分未確認リスク。 |
| 委託契約の適合 | 産業廃棄物処理委託契約書 | 品目・数量の範囲/処理方法/受託者・施設名/委託期間/料金・費用負担 | 契約外処理は違法。マニフェストの記載とも整合が必要。 |
| マニフェスト(産業廃棄物管理票) | 紙マニフェスト控え または 電子マニフェストの受信記録 | 交付者(排出事業者)/品目・数量/運搬・処分の完了確認/保存期間(5年) | 未交付・未確認は行政指導や罰則の対象。 |
- 電子マニフェストの活用で、運搬・処分の完了確認や保存が効率化します(紙と電子の併用は避け、どちらかに統一)。
- 見積書の品目名称と、許可証・契約書・マニフェストの品目表記は統一する(例:「廃プラスチック類(内装材)」など)。
- 「事業系一般の許可しかない業者」や「一般廃棄物の許可で産業廃棄物を回収」する事例は典型的な違法パターンです。
排出事業者は最終処分までの確認責任(トレーサビリティ)を負います。許可・契約・マニフェストの三点が揃って初めて合法の委託になります。
違法な不用品回収業者の見分け方
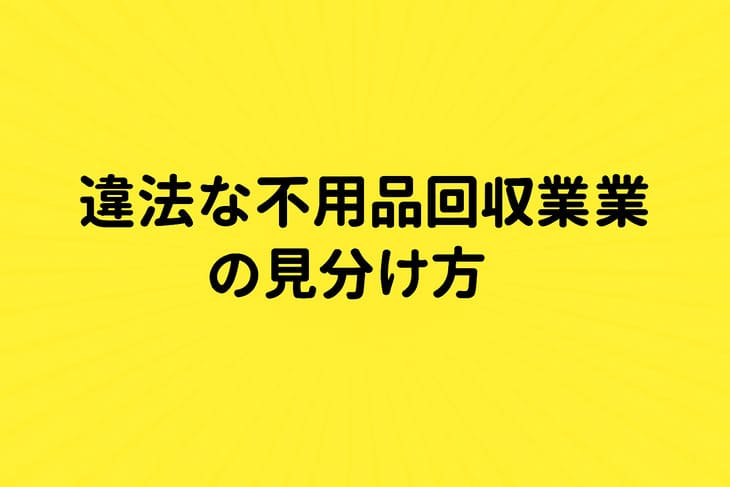
不用品の処分は、廃棄物の区分や許可の有無で適法・違法が分かれます。特に家庭から出る一般廃棄物は、原則として自治体または自治体から許可を受けた事業者(委託業者)しか収集・運搬できません。「無料回収」「なんでも回収」「積み放題」などの誘い文句に先行して依頼すると、無許可営業や不法投棄、高額請求のリスクが高まります。ここでは、典型的な見分け方、許可証の確認手順、書面でのチェックポイント、トラブル時の対処を体系的に解説します。
| チェック項目 | 適法な事業者の傾向 | 違法・悪質業者のサイン |
|---|---|---|
| 許可の種別・発行主体 | 家庭ごみの廃棄は「一般廃棄物収集運搬業許可(市区町村発行)」、事業系は排出地の自治体許可、産廃は「産業廃棄物収集運搬業許可(都道府県・政令市発行)」を保有 | 古物商許可のみ、または産廃許可しかないのに家庭ごみを回収。許可番号・発行主体の説明が曖昧 |
| 料金表示 | 事前見積りで内訳・数量基準・追加料金条件が明記。家電リサイクル料など公的費用は別途明示 | 「無料」「積み放題〇〇円」「当日限り」など根拠のない表示。口頭での概算のみ |
| 契約・書面 | 見積書・契約書・領収書を発行。事業者情報・許可番号・キャンセル条件が記載 | 書面がない、サインだけ求める、名刺・チラシに住所や固定電話がない |
| 車両・表示 | 社名・連絡先の表示、作業員の身分証、車両番号の提示に応じる | 無地の軽トラック、車両・制服に社名表示なし、身分証の提示を拒む |
| 回収方法 | 予約制の戸別収集。危険物・有害物の取扱い基準を説明 | 拡声器で巡回して即時積込み。分別不要・なんでも可と誘う |
| 支払方法 | 現金以外にも振込やカード対応、領収書は社印・内訳付き | 現金のみ・領収書を発行しない、社名のないレシート |
| 処分の透明性 | 処分先(中間処理・最終処分)を開示。再委託の有無や家電リサイクル券の扱いを説明 | 処分先が不明、「海外輸出」「無料で再利用」など抽象的説明のみ |
無許可の無料回収や軽トラック巡回の典型例
無許可営業の多くは、住宅街を軽トラックで巡回し「ご家庭の不要品を無料で回収します」と拡声器で呼びかけます。最初は無料・格安をうたう一方で、積み込み後に「分別費」「運搬費」「リサイクル費」など名目を追加して高額請求に転じるのが典型パターンです。チラシや車両、作業員の身なりに社名・所在地・許可番号が見当たらない場合は特に要注意です。
| 広告・行動のサイン | 背景 | 想定されるリスク |
|---|---|---|
| 「無料回収」「地域最安値」「なんでも回収」 | 適正処理には運搬・処分コストが発生し、恒常的な無料は成立しにくい | 積込み後の高額請求、不法投棄、個人情報機器の流出 |
| 「軽トラック積み放題〇〇円」 | 容量・重量・品目の基準が曖昧で、現場で「規格外」として追加請求の余地 | 口頭合意との差、法外な追加費用、荷下ろし拒否 |
| 拡声器で巡回・即日その場で積込み | 予約・許可管理のない突発営業は無許可の可能性が高い | 許可不備、事故時の責任所在不明、近隣トラブル |
| チラシや名刺に住所・固定電話・許可番号なし | 連絡遮断を前提とした営業 | 後日連絡不能、返金・苦情対応不可 |
| 支払いは現金のみ・領収書なし | 痕跡を残さない意図 | 証拠不十分での紛争、税務・会計書類として無効 |
これらのサインが複数当てはまる場合は依頼を控え、自治体の回収や、許可を持つ適正事業者の見積りを取り直すのが安全です。
許可証と許可番号の確認方法
業者選定で最も確実なのが許可証の確認です。契約・積込みの前に、許可証の原本または写しの提示を求め、許可番号・発行主体・有効期限・許可品目・許可の区域を必ず控えてください。以下の対応関係を把握しておくと判別が容易です。
| 処理内容 | 必要な許可 | 発行主体 |
|---|---|---|
| 家庭から出る一般廃棄物を「廃棄目的」で収集・運搬 | 一般廃棄物収集運搬業許可(該当市区町村) | 市区町村 |
| 事業所から出る一般廃棄物の収集・運搬 | 一般廃棄物収集運搬業許可(排出地の市区町村) | 市区町村 |
| 産業廃棄物の収集・運搬 | 産業廃棄物収集運搬業許可 | 都道府県・政令市 |
| 不用品の買い取り・リユース(転売目的) | 古物商許可 | 都道府県公安委員会 |
確認手順は次の通りです。1) 許可証の提示を受け、社名・所在地・代表者・許可番号・有効期限・許可の区域・許可品目を照合する。2) 家庭ごみの回収目的なら「一般廃棄物収集運搬業許可(あなたの自治体名)」であることを確認する。3) 産業廃棄物許可や古物商許可しか提示されない場合は、家庭ごみの収集はできない旨を認識する。4) 車両番号・作業員の身分証、見積書の事業者情報と許可証の記載が一致するか確認する。5) 家電リサイクル対象品の回収では、リサイクル料金・収集運搬料金の説明やリサイクル券手続きの案内があるかをチェックする。
「古物商許可があるので大丈夫」「産廃許可があるので家庭ごみも回収できる」といった説明は誤りです。許可の種類と対象は厳密に分かれているため、用途に合致しない許可での回収は違法になります。
見積書や契約書で見るべき項目
トラブルの多くは「口頭説明のみ」「金額の内訳不明」から発生します。書面に何が、どこまで、いくらで、どの条件で含まれるのかを明記させましょう。特に数量基準(個数・体積・重量)、追加費用の発生条件、キャンセル条件は必須です。
| 書面項目 | 具体的に記載すべき内容 | 不備がある場合のリスク |
|---|---|---|
| 事業者情報 | 法人名(屋号)、所在地、代表者、連絡先(固定電話)、担当者名 | 連絡不能、所在不明での紛争化 |
| 許可情報 | 許可種別(一般/産業/古物)、許可番号、有効期限、発行主体 | 無許可・対象外許可での回収 |
| 回収日時・場所 | 訪問日時、住所、搬出経路・駐車条件 | 当日の不在・近隣トラブル・追加請求 |
| 品目・数量 | 品目ごとの個数/容量/重量、家電リサイクル対象の有無 | 「想定外」名目の追加料金 |
| 料金内訳 | 基本料金、出張費、搬出・人件費、階段・養生費、車両費、リサイクル料、消費税 | 不明瞭会計、高額請求 |
| 追加費用条件 | 当日追加の発生要件と上限、再見積りの手順 | 現場での一方的な上乗せ |
| 作業範囲 | 分別・解体・養生・清掃の有無、危険物の扱い | 想定外作業の有償化 |
| キャンセル条件 | 前日/当日/積込後のキャンセル料と算定基準 | 不当に高い違約金 |
| 処分方法・処分先 | 中間処理業者・最終処分場の名称(可能な範囲で) | 不法投棄、追跡不能 |
| 支払方法・書類 | 支払手段、領収書の発行、事業者は請求書・適格請求書の要否 | 証憑不備、経理上の問題 |
| 個人情報の保護 | PC・スマホのデータ消去方法と証明書の発行可否 | 情報漏えい |
| 再委託 | 再委託の有無、範囲、事前承諾 | 責任の所在不明 |
見積書に記載のない追加請求や、契約前に合意していない作業費は支払わないのが原則です。その場でのサインや支払いを求められても、書面の再作成と説明を要求しましょう。
不法投棄や高額請求への対処と相談先
万が一、積み込み後の高額請求や不法投棄の疑いが生じた場合は、感情的に応じず、証拠を確保し、しかるべき窓口に相談します。支払い前に見積書・契約書・領収書の整合を確認し、合意のない請求には理由と根拠書面の提示を求めるのが基本です。威圧的な言動や居座りがあれば安全確保を最優先にしてください。
| 状況 | 取るべき行動 | 残すべき証拠 |
|---|---|---|
| 積込み後の高額請求 | 見積書との差額理由を明文化させ、合意のない費用は支払わない。必要に応じてその場での支払いを拒否し、後日精査を伝える | 見積書・契約書・請求書、会話のメモ、録音、作業中の写真 |
| 威圧・脅迫・不退去 | 身の安全を優先し、家族や近隣に助けを求め、警察に通報 | 相手の言動記録、車両番号、作業員の特徴 |
| 不法投棄の疑い・目撃 | 自治体の環境部局へ通報。契約先・日時・品目を伝える | 領収書、業者情報、現場写真、時刻 |
| 契約書面が交付されない | 書面交付を再度要求。応じない場合は依頼を中止し、後日相談窓口へ | 名刺・チラシの写真、やり取りの記録 |
| PC・スマホの処分 | データ消去の方法・証明書の発行可否を確認し、不安なら回収前に自分で初期化 | データ消去証明書、消去手順の記録 |
なお、事業所からの排出(事業系一般廃棄物や産業廃棄物)の場合、排出事業者に法的責任(委託基準の遵守など)が伴います。契約・許可確認・処分先の把握を徹底し、必要に応じて専門部署(総務・法務)での確認を挟みましょう。
消費者ホットラインと各自治体の相談窓口
困ったときは一人で抱え込まず、早めに公的窓口へ相談します。消費生活に関するトラブルは、消費者ホットライン「188」(いやや!)に電話すると、最寄りの消費生活センターにつながります。料金トラブルや強引な勧誘、書面不交付などの相談に対応しています。
違法な回収や不法投棄の通報は、各市区町村の環境部局(資源循環課・清掃事務所・環境政策課など)に連絡します。無許可の巡回回収の情報(車両番号、日時、場所、広告の文言)や、許可の有無が疑わしい業者に関する情報提供も有効です。
威圧的な請求、居座り、脅迫など身の危険がある場合は、ためらわず警察に通報してください。相談の際は、業者名・連絡先・許可番号、見積書・契約書・領収書、車両番号や作業員の特徴、やり取りの記録(録音・写真・時刻)を準備しておくと、対応がスムーズです。
「許可証の確認」「書面の整備」「不審点はその場で即決しない」という三原則を徹底すれば、多くのトラブルは未然に防げます。不安があれば、まずは自治体や消費生活センターに相談し、適正処理につながるルートを選びましょう。
正しい処分の手順と具体的な流れ

不用品の処分は、自治体ルールと廃棄物処理法に沿って「分類→予約(もしくは持込準備)→費用確認→搬出→受け渡し→証憑保管」という順序で進めると、余計なコストやトラブルを避けられます。対象が家庭ごみか事業系一般廃棄物かによって手順が異なるため、最初に区分を明確にし、自治体の案内に従って進めましょう。
家電リサイクル法やパソコンリサイクルの対象品は自治体の粗大ごみでは原則出せないため、対象外品の有無を必ず先に確認することが、最短・最安での処分につながります。
家庭の粗大ごみを自治体で出す手順
家庭から出る粗大ごみの戸別収集は、申し込みと手数料の前払い、指定日の屋外排出が基本です。自治体により運用は異なりますが、概ね次の流れで進みます。
| ステップ | やること | 具体例 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 1. 区分確認 | 品目が粗大ごみに当たるかを確認 | 家具・寝具・自転車・健康器具など | 家電リサイクル法対象(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機)やPCは別手順 |
| 2. 予約 | 電話・ウェブ・窓口で申し込み | 住所、氏名、品目、サイズ・数量、希望日、排出場所を伝える | 受付番号や収集日が付与されるので控える |
| 3. 手数料 | 粗大ごみ処理券を購入し必要事項を記入 | コンビニエンスストア・スーパー・市役所/区役所で購入 | 券種と金額は品目ごとに異なる。券の再発行は不可が一般的 |
| 4. 準備 | 搬出しやすい状態にする | 分解・紐で結束・付属品の取り外し | ガラス・刃物は養生して危険表示。中身は空にする |
| 5. 排出 | 指定日の朝までに指定場所へ出す | 処理券をよく見える位置に貼付 | 集合住宅は管理ルールに従い、共用部の通行を妨げない |
| 6. 証憑保管 | 受付控え等を一定期間保管 | 受付メールやメモ、領収書 | トラブル時の証跡になるため保管推奨 |
粗大ごみ処理券の貼付や受付番号の管理を怠ると収集対象外となる場合があります。申し込み時の指示に従い、記入・貼付・排出時刻を厳守してください。
申込み方法と手数料券の購入
予約は自治体の指定する窓口で行います。一般的には電話、ウェブ申込み、窓口申請のいずれかで受け付けています。予約後、指定の手数料分の粗大ごみ処理券(有料ごみ処理券)を購入し、券面に指示された項目(氏名または受付番号、収集日・品目など自治体指定の情報)を油性ペンで記入、品目の見やすい位置に貼付します。
| 申込み方法 | 特徴 | 主な入力・確認事項 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 電話 | オペレーターと確認できるため品目判定が確実 | 住所、氏名、連絡先、品目・サイズ、数量、排出場所 | 混雑時間帯はつながりにくいことがある |
| ウェブ | 24時間申込み可能な自治体もあり手早い | 品目選択、搬出予定、受付メールの保存 | 入力ミスや迷惑メール振分けに注意 |
| 窓口 | その場で不明点を解消できる | 本人確認書類の提示を求められることがある | 開庁時間内のみ。持参品の確認を事前に |
粗大ごみ処理券は、多くの自治体でコンビニエンスストアやスーパー、市役所・区役所の売り場で購入できます。券種と金額は品目ごとに異なるため、予約時の案内に従い必要金額分を用意してください。
家電リサイクル法対象品目は粗大ごみ処理券では出せません。販売店引取りまたは指定引取場所への搬入と、家電リサイクル券の手続が必要です。
搬出の注意点と収集日当日の流れ
収集日当日は、指定された時間までに屋外の指定場所(戸建ては玄関先や道路沿い、集合住宅は所定の集積場所など)に排出します。雨天でも原則収集は実施されますが、飛散・破損防止のため、券が剥がれない位置に貼り、必要に応じて養生します。
搬出時は、通路・階段・エレベーターの養生や、深夜・早朝の騒音配慮が必要です。分解できるものは事前に解体し、ネジ・金具・ガラスなどはテープで固定します。危険物(刃物、鏡・ガラス、蛍光管など)は「キケン」表示をし、安全に配慮してください。
| よくある不適合例 | 起きやすい理由 | 対策 |
|---|---|---|
| 処理券未貼付・金額不足 | 券種の選択ミス、貼付忘れ | 予約内容と券種を再確認し、見やすい位置に貼付 |
| 屋内排出のまま | 自治体の原則「屋外排出」を失念 | 指定場所へ自力搬出。支援が必要な場合は事前相談 |
| 危険物の未養生 | ガラス・刃物の露出 | 厚紙やプチプチで保護し「キケン」表示 |
| 対象外品の混入 | 家電リサイクル品やPCを同時排出 | 対象外は別ルートで手続き。混載しない |
立会い不要が一般的ですが、収集員の安全確保のため、通行の妨げや不法投棄と誤解される置き方は避け、管理規約・掲示案内に従って排出しましょう。
クリーンセンターや持込施設への自己搬入
持込施設(クリーンセンター、資源化センター等)に自己搬入する場合は、施設の受入基準・予約要否・手数料・搬入可能時間を事前に確認します。多くの施設では、計量→受付→荷下ろし→再計量→精算の順で処理され、料金は重量や品目で決まります。
| 段階 | やること | 持ち物・確認事項 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 事前確認 | 施設の受入品目と予約可否を確認 | 住所地の確認(居住者限定の施設が多い) | 家電リサイクル品・PCなど対象外品は持ち込めない |
| 来場 | ゲートで受付・計量 | 本人確認書類、車両、現金またはキャッシュレス(施設規程による) | 積載物は飛散防止を徹底。ヘルメット・手袋など安全装備を推奨 |
| 荷下ろし | 指示されたヤードで搬入・分別 | スタッフの指示に従い危険物は個別対応 | 混載は不可の場合あり。分別表示に従う |
| 精算 | 再計量後に手数料を支払い退場 | 領収書の受領と保管 | 最低料金設定がある施設もある |
自己搬入は予約枠や受入制限が設けられることがあるため、当日の持込可否と必要書類を事前に確認してから出発してください。
リユースと買取を優先する判断基準
処分コストと環境負荷を減らすには、再使用(リユース)や買取の可能性を先に検討します。動作状態、年式、付属品の有無、外観コンディション、相場需要が判断材料です。清掃・動作確認・付属品の揃え込みで評価が改善します。
| 品目 | リユース/買取の目安 | チェックポイント | 事前準備 |
|---|---|---|---|
| 家電(小型) | 動作品で年式が新しいほど有利 | 動作、年式、取扱説明書・箱の有無 | 清掃、簡易動作確認、付属品をまとめる |
| 家具 | 人気デザイン・有名メーカーは評価されやすい | 傷・汚れ・がたつき、サイズ | 拭き上げ、分解可否の確認、採寸 |
| パソコン | 動作品・外観良好なら宅配回収や下取りが現実的 | 起動可否、ストレージ容量、付属品 | データ消去(初期化)、アカウント解除 |
| 子ども用品 | 使用期間が短く状態良好なら需要あり | 安全基準・リコール有無、汚れ | 丸洗い・除菌、取扱説明書の同梱 |
| スポーツ用品 | 人気競技・シーズン品は動きやすい | 劣化・破損、メーカー・型番 | クリーニング、型番のメモ |
データを含む機器は、初期化・データ消去を完了してから買取や譲渡に出すことが必須です。査定不可品や安全上リユース不適の品は、適切に一般廃棄物として処分しましょう。
古物商許可の有無と買取時の留意点
買取を行う事業者には古物営業法に基づく古物商許可が必要です。店舗・ウェブ・広告などに「古物商許可番号」と管轄の公安委員会名の表示があり、提示に応じられるかを確認します。訪問買取などの取引では、書面交付や本人確認の手続が求められます。
| 確認すべき表示・書類 | 確認ポイント | 受け取り後の管理 |
|---|---|---|
| 古物商許可番号 | 公安委員会名と番号の表示があるか | 控えを撮影・保存しておく |
| 買取明細(レシート・契約書) | 品目・数量・金額・日付・事業者情報の記載 | 返品・問い合わせに備え保管 |
| 本人確認手続 | 運転免許証等の提示依頼が適切か | 個人情報の取扱い説明の有無を確認 |
「回収ついでの現金買取」をうたう事業者を利用する場合は、古物商許可と領収書の発行可否を必ず確認し、無許可・無明細での引渡しは避けましょう。
事業系の正しい委託手順
事業活動に伴って生じる一般廃棄物(事業系一般廃棄物)は、排出事業者が責任をもって適正に処理する必要があります。多くの自治体では、自治体が許可した事業系一般廃棄物収集運搬業者と委託契約を結び、定期またはスポット収集を行います。
委託にあたっては、分別方針(可燃・不燃・資源)、排出量の見込、保管場所、収集頻度、料金体系(容器・重量・回数ベースなど)を整理し、見積依頼の際に情報提供します。契約後は、集積所や鍵の取り扱い、収集曜日・時間帯、緊急時の連絡系統を取り決め、領収書・処分証明書等の証憑を保管します。
事業系一般廃棄物の回収は、家庭ごみのルールと異なり、許可業者との委託契約と適正な分別・保管が前提です。
見積りから最終処分までのフロー
| 段階 | 目的 | 排出事業者の対応 | 業者からの提示/発行物 |
|---|---|---|---|
| 1. 現地調査 | 品目・量・分別の把握 | 平面図や排出場所、搬出経路の情報提供 | 調査結果の共有、必要機材の提案 |
| 2. 見積・契約 | 費用・頻度・体制の確定 | 見積比較・条件確認・委託契約書への署名 | 見積書、委託契約書、許可証の写し |
| 3. 分別・保管 | 適正分別と安全な一時保管 | 社内ルール化、表示・容器の設置 | 分別ガイド、容器・ラベルの提供 |
| 4. 収集・運搬 | 計画どおりの回収 | 排出時間・場所の遵守、立会い(必要時) | 収集記録、領収書の発行 |
| 5. 中間処理・資源化 | 再資源化・減量化 | 特別な要望があれば事前共有 | 処理工程の説明、施設情報 |
| 6. 処分完了 | 証憑整備と監査対応 | 領収書・処分証明書の保管 | 処分証明書(必要に応じて) |
上記のフローを文書化して運用すると、担当者交代時も処理が滞りません。自治体基準に適合する許可業者を選び、許可番号・契約書・領収書・処分証明書を揃えて管理することが重要です。
具体例で学ぶ不用品回収と一般廃棄物の線引き

この章では、実際に迷いやすい場面を想定し、「どこまでが一般廃棄物(家庭系・事業系)として自治体や許可業者に委託できるのか」「いつ産業廃棄物としてマニフェストや収集運搬業許可が必要になるのか」を、品目・状況別に具体化します。判定の基本は、排出主体(家庭か事業者か)、発生状況(日常の片付けか工事伴いか)、品目(リサイクル制度対象か)、委託先の許可の有無です。
家庭から出る一般廃棄物は自治体(または自治体の許可・委託を受けた業者)以外は収集運搬できません。事業所から出るごみは、日常系は「事業系一般廃棄物」、工事・解体・内装に伴う廃材は「産業廃棄物」となるのが原則です。特定家電やパソコンは専用のリサイクル制度を優先します。
| 判定の観点 | 典型例 | 区分の目安 | 必要な手続・書類 |
|---|---|---|---|
| 排出主体 | 家庭の片付け・引越し | 家庭系一般廃棄物 | 自治体粗大ごみ申込み・手数料券、各種リサイクル手続 |
| 排出主体 | オフィスや店舗の日常排出 | 事業系一般廃棄物 | 自治体許可業者との委託契約書、許可番号の確認 |
| 発生状況 | 内装工事・什器撤去・解体 | 産業廃棄物 | 産業廃棄物収集運搬業許可・処分業許可、マニフェスト |
| 品目の制度 | 特定家庭用機器・小型家電・PC | 各リサイクル制度に従う | 家電リサイクル券、回収申込み控え、PCリサイクル手続 |
引越しの家財整理
引越しで発生する家財は、原則として家庭系一般廃棄物です。多くは自治体の「可燃・不燃・資源ごみ」や「粗大ごみ」で処理し、法律で指定された家電・パソコンは専用ルートでリサイクルします。引越し業者や不用品回収業者にまとめて依頼する場合でも、一般廃棄物の収集運搬は自治体の許可・委託が必要であり、無許可の引取りは依頼側もトラブルの原因になります。
| 品目・状況 | 区分 | 処理ルート・根拠 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| ソファ・ベッド・マットレス・タンス | 家庭系一般廃棄物(粗大ごみ) | 自治体粗大ごみ受付で申込み、手数料券を貼付 | 集合住宅の場合は搬出経路や収集日を管理会社に確認 |
| エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機 | 家電リサイクル法対象 | 販売店引取りまたは指定引取場所へ搬入、家電リサイクル券 | 自治体の収集対象外。事前にリサイクル料金と運搬手配を確認 |
| 電子レンジ・炊飯器・掃除機・ドライヤー・ゲーム機など | 小型家電リサイクル法対象(自治体運用に従う) | 回収ボックス・拠点回収・収集申込み | 充電池は外し、電池は有害ごみ・拠点回収へ |
| パソコン本体・ディスプレイ | PCリサイクル(家庭用) | メーカー回収に申込み(PCリサイクルマーク付は無償が基本) | データ消去を自己責任で実施し、申込控えを保管 |
| 自転車 | 家庭系一般廃棄物(粗大ごみ) | 自治体粗大ごみ受付、または再使用可能ならリユース | 防犯登録抹消を済ませる |
| スプレー缶・ライター・ボタン電池・蛍光灯 | 有害ごみ・拠点回収 | 自治体ルールに従って分別・持込み | 穴あけ禁止の自治体あり。発火に注意 |
| 土・砂・コンクリート片・石 | 自治体収集対象外が一般的 | 受入可否はクリーンセンター規定次第 | 受入不可の場合は専門業者に相談(産業廃棄物になることがある) |
| まだ使える家具・家電 | リユース・買取 | 古物商許可のある事業者による出張買取・店頭買取 | 年式・状態で買取不可なら自治体処理へ切替 |
家庭の一般廃棄物を、自治体の許可がない不用品回収業者へ一括で引渡すことはできません。残置物の運搬を依頼する際は、自治体名が入った一般廃棄物収集運搬の許可証・許可番号を確認しましょう。
遺品整理と生前整理
遺品整理・生前整理は家庭由来の品目が中心で、基本は家庭系一般廃棄物として自治体ルールで処分します。遺品整理業者に作業を依頼する場合でも、一般廃棄物の収集運搬には自治体の許可が必要です。貴金属・ブランド品・骨董などは古物商による買取、家電・PCは各リサイクル制度を優先します。
| 品目・状況 | 区分 | 処理ルート・根拠 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 家具・寝具・生活雑貨 | 家庭系一般廃棄物(粗大ごみ・可燃/不燃) | 自治体収集・持込み | 大量排出時は収集回数や持込み制限を事前確認 |
| 仏壇・位牌・写真アルバム | 家庭系一般廃棄物(自治体ルール優先) | 不燃/可燃で分別。希望により供養を手配 | 金属装飾は取り外し。供養は任意で費用が発生 |
| 家電4品目・その他家電 | 家電リサイクル法・小型家電リサイクル | 販売店引取り・指定引取場所・回収ボックス | リモコン・ケーブルも忘れず同梱 |
| パソコン・スマートフォン・タブレット | PCリサイクル・小型家電リサイクル | メーカー回収または回収ボックス | データ消去・初期化、記録メディアの別回収 |
| 在宅医療由来の鋭利物(注射針等) | 自治体収集対象外 | 処方先の医療機関・薬局に相談 | 一般ごみに混ぜない |
| 自営業で使用していた工具・機材の一括処分 | 産業廃棄物になる場合 | 産業廃棄物許可業者へ委託、マニフェスト | 家庭分と事業分を混合しないよう分別 |
遺品整理業者に運搬まで依頼する場合は、作業実績だけでなく「一般廃棄物収集運搬の許可の有無(自治体名・許可番号)」と、買取を行う場合の「古物商許可」を必ず確認してください。
オフィス家具とパソコンの更新
オフィスの更新で出る廃棄物は、日常的な入替え・少量排出なら事業系一般廃棄物として自治体の許可業者に委託するのが一般的です。一方、フロアの原状回復や内装解体を伴う一括撤去では、混合廃棄物や建設系残材が発生し、産業廃棄物としての手続(許可確認・マニフェスト)が必要になります。PCは事業所用のメーカー回収が基本で、データ消去を排出事業者の責任で実施します。
| 品目・状況 | 区分 | 処理ルート・根拠 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| デスク・チェア・ロッカー・書庫 | 事業系一般廃棄物(自治体運用による) | 自治体許可の一般廃棄物収集運搬業者と委託契約 | 自治体により持込みのみ対応・数量制限があるため事前確認 |
| パソコン・モニター・社用携帯 | 事業所向けメーカー回収 | メーカーに回収申込み(有償が一般的) | データ消去証明の発行可否、資産管理台帳の更新 |
| 複合機・プリンター・シュレッダー | 事業系一般または産業廃棄物 | リース会社の引取が基本。不可の場合は適切な許可業者へ | 重量物は搬出養生が必要。トナー等は別途回収 |
| 機密文書・カルテ・帳票 | 事業系一般(機密抹消処理) | 溶解処理・破砕処理の委託、処理証明書を保管 | 回収容器の封緘・立会いルールを社内規程に明記 |
| 原状回復・内装解体に伴う什器・床材・壁材 | 産業廃棄物(混合廃棄物・木くず・廃プラスチック類 等) | 産業廃棄物収集運搬業者・処分業者へ委託、マニフェスト | 収集運搬業許可と処分業許可の品目適合・許可番号を確認 |
オフィスの一括撤去や解体を含む案件は「産業廃棄物」の扱いとなるのが一般的で、排出事業者がマニフェストの交付・保存を行います。見積段階で委託契約書の有無と許可証の写しを確認しましょう。
店舗什器の入れ替え
店舗のリニューアルでは、陳列棚などの日常的な入替えは事業系一般廃棄物、内装工事や大規模撤去を伴うと産業廃棄物になります。業務用の冷凍冷蔵機器は廃棄前にフロン類回収が必要となるため、専門の回収業者による証明書類を整えたうえで廃棄工程に進みます。
| 品目・状況 | 区分 | 処理ルート・根拠 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 陳列棚・ハンガーラック・ワゴン | 事業系一般廃棄物(自治体運用による) | 自治体許可の一般廃棄物収集運搬業者に委託 | サイズ・数量で持込み限定となる場合あり |
| 業務用冷蔵庫・製氷機・ショーケース | 産業廃棄物(フロン類回収が先行) | フロン回収後、適正な許可業者が収集運搬・処分 | フロン回収証明の保管、搬出時の養生・重量対応 |
| レジ・POS・決済端末 | 事業系一般または小型家電リサイクル | 自治体ルールまたは回収スキームに従う | 個人情報・取引データの消去と証跡保管 |
| 内装材(床・壁・天井)・カウンターの解体 | 産業廃棄物(がれき類・木くず 等) | 産業廃棄物許可業者へ委託、マニフェスト | 工事請負側の分別計画と処分先の適合確認 |
| 賞味期限切れ食品・残渣 | 事業系一般廃棄物 | 自治体の収集・持込み(生ごみルールに従う) | 漏えい・臭気対策、重量物は水切りを徹底 |
店舗リニューアルで什器撤去と内装解体が同時に発生する場合は、産業廃棄物としての委託契約とマニフェストが不可欠です。業務用冷凍冷蔵機器はフロン回収を先に実施し、その証明書を原処理記録として保管してください。
以上の具体例を踏まえ、同じ「不用品回収」でも、家庭か事業か、工事を伴うか、法律で指定された品目かによって適正な処分ルートは変わります。疑義がある場合は、自治体の担当課(清掃事務所・資源循環課等)に品目と排出状況を伝えて確認し、必要に応じて自治体許可の一般廃棄物収集運搬業者または産業廃棄物処理業者へ委託してください。
よくある質問

自治体の回収と民間業者の回収の違い
自治体の回収は、市区町村の条例や収集基準に基づく公的サービスで、家庭から出る一般廃棄物(可燃ごみ・不燃ごみ・資源ごみ・粗大ごみなど)を対象にしています。一方、民間の不用品回収や一般廃棄物収集運搬業者は、自治体が許可した区域・品目・方法の範囲で業務を行う有料の委託サービスです。産業廃棄物の収集運搬には別枠の許可が必要で、取り扱い区分と許可の種類を混同しないことが重要です。
最も大きな違いは「誰が、どの法的根拠で、どの範囲を収集できるか」です。自治体回収は公的枠組み、民間回収は許可に基づく委託であり、対象品目や書類の取り扱いも異なります。
| 項目 | 自治体(市区町村)の回収 | 民間業者の回収 |
|---|---|---|
| 位置づけ・法的根拠 | 市区町村の直営または委託事業。廃棄物処理法と各自治体の条例に基づく。 | 自治体の「一般廃棄物収集運搬業許可」または「産業廃棄物収集運搬業許可」に基づく有料サービス。 |
| 取扱品目 | 家庭系一般廃棄物(可燃・不燃・資源・粗大ごみ)。家電リサイクル法対象品やPCは原則不可。 | 許可の範囲内の一般廃棄物、または産業廃棄物。家電リサイクル法対象品は適正ルートでの引取りに限り可。 |
| 料金 | 手数料券(粗大ごみ処理券)など定額制が中心。戸別収集は低廉。 | 品目・数量・搬出作業・階段搬出・養生などで見積り算定。収集運搬料や処分費が発生。 |
| 搬出対応 | 原則として自宅外の指定場所に自己搬出。屋内からの搬出は行わないのが一般的。 | 屋内からの搬出、解体、養生、時間指定など柔軟に対応(別料金)。 |
| 事業系一般廃棄物 | 市区町村が定めた業者との契約制。指定収集袋や排出ルールあり。 | 排出場所の市区町村で一般廃棄物許可を持つ業者のみ委託可。許可外業者は違法。 |
| 家電リサイクル法対象品 | 収集不可。指定引取場所や販売店引取り案内へ誘導。 | リサイクル料金の支払いと家電リサイクル券(管理票)の発行・運搬を適正に行う場合のみ可。 |
| 書類 | 領収書など。マニフェストは不要。 | 領収書・見積書・契約書。産業廃棄物はマニフェスト(紙または電子)が必須。 |
| 受付方法 | 粗大ごみ受付センターや自治体窓口で予約・手数料券購入。 | 電話・Webで見積り予約。現地見積りで確定が一般的。 |
| リユース・買取 | 原則なし(リユースは自治体運営のリサイクルプラザ等に限られる場合あり)。 | 古物商許可を持つ業者のみ買取可。有価物として再流通する場合は適切な台帳管理が必要。 |
自治体の対象外品(家電リサイクル法対象品やPC、危険物など)は、法に適合した民間ルートで手続きするのが基本です。
無料回収のリスク
「無料回収」や「軽トラックで巡回中、何でも引き取ります」といった勧誘は、無許可営業や不適正処理につながる典型例です。廃棄物処理法には「無料なら無許可でよい」という例外はなく、一般廃棄物は市区町村許可、産業廃棄物は都道府県許可が必要です。許可のない回収は違法で、不法投棄や高額請求のトラブルが後を絶ちません。
無料や格安をうたう無許可回収は、不法投棄・高額請求・個人情報漏えいのリスクが高く、委託先として避けるべきです。
- 典型的な注意サイン:許可番号や許可証の提示がない、社名・所在地が不明、見積書・領収書が出ない、「何でも無料」を強調。
- 家電リサイクル法対象品を無料で引き取ると称し、後から運搬費などを追加請求する事例。
- データ機器(パソコン・外付けHDD・スマートフォン)の無管理回収による情報漏えい。
回避策として、許可の種類(一般廃棄物収集運搬・産業廃棄物収集運搬・古物商)と許可番号、代表者名、許可の有効期限を事前に確認し、書面の見積書・契約書・領収書の発行を条件にしましょう。データ機器は、初期化や物理破壊などのデータ消去対策を行い、可能ならば証明書の発行を受けてください。
適正な料金提示(見積書)と適法な許可・書類の整備が、トラブルを未然に防ぐ最善策です。
家電リサイクル券の購入場所
家電リサイクル法の対象品(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)を処分する際は、製品ごとに定められたリサイクル料金を支払い、家電リサイクル券(管理票)を発行して適正ルートで回収・引取りを受けます。新しい製品を購入する場合は小売業者に引取り義務があり、買い替え時は販売店に依頼するのが最も簡単です。
| 取得場所 | 想定ケース | 手続き内容 | 支払い |
|---|---|---|---|
| 家電量販店・購入店 | 買い替え時、または同等機種の引取りを依頼する場合 | 店舗でリサイクル料金の案内と家電リサイクル券の作成。収集運搬も手配可。 | 店頭でリサイクル料金と収集運搬料をまとめて支払い |
| 郵便局(ゆうちょ銀行)窓口 | 買い替えではない処分や、自分で指定引取場所へ持ち込む場合 | 所定の振替用紙でリサイクル料金を振込し、家電リサイクル券(管理票)を取得 | 窓口でリサイクル料金を支払い(運搬は別途手配) |
郵便局で家電リサイクル券を用意した場合は、券面に記載の指定引取場所へ自己搬入するか、自治体の案内に従い適法な収集運搬業者へ運搬を依頼します。引取り後は、家電リサイクル券(管理票)の控えと領収書を保管してください。
買い替えは販売店手続き、買い替え以外は郵便局での支払いと指定引取場所への搬入が基本です。
県外業者に委託する際の注意点
「県外の安い業者に頼めるか」という相談は多いですが、許可の有無と許可の有効区域が最優先の確認事項です。一般廃棄物は市区町村が許可権者であり、排出場所の市区町村で許可を持たない業者は収集できません。産業廃棄物は都道府県(または政令市)ごとの許可が必要で、跨ぐ全ての区域での許可確認とマニフェストの発行が求められます。
| 廃棄物区分 | 県外業者への委託 | 最低限の確認事項 | よくある誤解 |
|---|---|---|---|
| 家庭系・事業系の一般廃棄物 | 排出場所の市区町村で一般廃棄物収集運搬業許可を持つ場合のみ可 | 市区町村名が入った許可証、許可番号、有効期限、収集区域・品目 | 県の許可があれば一般廃棄物も運べるという誤解(実際は市区町村許可が必要) |
| 産業廃棄物 | 跨ぐ全ての都道府県・政令市で収集運搬業許可を取得していれば可 | 各区域の許可証、運搬車両表示、積替え保管の有無、マニフェストの発行 | 排出地の許可だけで全国運搬できるという誤解(実際は通過・搬入先の許可も必要) |
| 家電リサイクル法対象品 | 適切なリサイクル手続きと運搬体制が整っていれば可 | 家電リサイクル券(管理票)、指定引取場所への運搬、領収書・控えの交付 | 無料回収であれば法手続き不要という誤解(実際は料金支払いと管理票が必要) |
メーカー等が広域的に回収する「広域認定制度」や、小型家電リサイクル法の認定事業者など、特例的に越境収集が認められる制度もありますが、一般の不用品回収や事業系一般廃棄物には原則適用されません。委託前に許可証の提示を受け、見積書・契約書・領収書、(産業廃棄物の場合は)マニフェストを確実に取り交わしましょう。
県外かどうかではなく「排出場所で有効な許可」と「必要書類の整備」が委託判断の基準です。
まとめ

結論として、環境省の基準に照らすと、家庭の一般廃棄物の収集・運搬は廃棄物処理法により、市区町村か、市区町村の許可・委託を受けた一般廃棄物収集運搬業者のみが行えます。「不用品回収」は法的用語ではありませんので、無許可の無料回収や軽トラック巡回の利用は避けてください。
事業活動で生じたごみは品目により事業系一般廃棄物か産業廃棄物に分かれます。前者は自治体許可業者と契約し、後者は都道府県等の許可業者へ委託してマニフェストを交付します。排出者責任の下、最初に適切な区分を確認することが要点です。
適正ルートは、粗大ごみは自治体申込みと手数料券、家電リサイクル法の4品目は小売店引取り・指定引取場所、小型家電リサイクル法の対象は自治体回収、パソコンはメーカー回収の活用です。再使用可能品はリユース・買取を優先し、買取事業者の古物商許可をご確認ください。
業者選定では許可証(番号・品目・区域・有効期限)と見積・契約、最終処分方法の書面確認が重要です。不法投棄や高額請求が疑われる場合は、消費者ホットライン(188)や警察総合相談(#9110)、各自治体の相談窓口へ早めにご相談ください。適正処理の基本を守ることが、合法・安全・経済的な不用品処理への最短経路です。
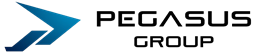
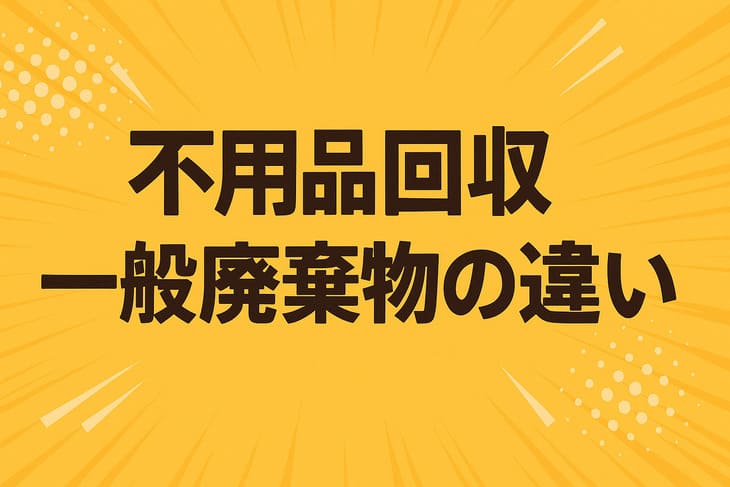

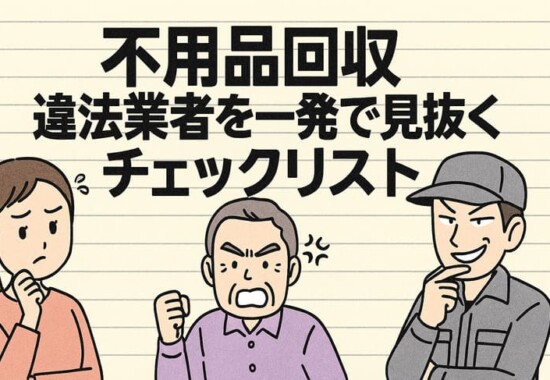


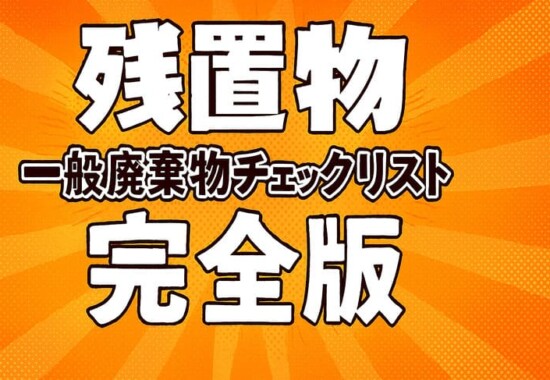

この記事へのコメントはありません。